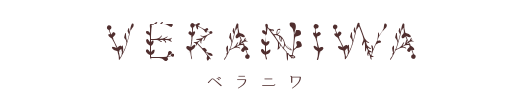自作のぼかし肥料をベランダ菜園に使用し続けて、4年ほど経ちました。
ベランダで育てている野菜にもバラの花にも使用しています。
ぼかし肥料作りについては試行錯誤し、今までに何度か記事にもしてきました。
現在は、手も汚さずに作れる簡単で楽な作り方、そして何にでも使用しやすい配合に落ち着きました。
そこで、私のぼかし肥料作りの完成形ということで、記事にまとめたいと思います!
ビニール袋に入れて口を閉じる嫌気発酵での作り方になります。
※「ぼかし肥料とは?」「なぜぼかし肥料を作るのか?」「嫌気発酵と好気発酵の違い」については、過去記事に書いてありますので、気になる方はご覧下さい↓
ぼかし肥料の材料

材料は、以下です。
米ぬか&油かす
米ぬかと油かすの量は、個人的には米ぬか:油かす=3:1がおすすめ。(例:米ぬか1500g、油かす500g)※詳しくは肥料の配合の項目で後述します
米ぬかは、こだわりのものを購入してもいいし、近くにコイン精米機があって貰えるようなら貰ってきてもいいし、お米屋さんで入手したものでもOKです。
油かすや腐葉土は、ホームセンターなどで売られています。
私は、マルタ一番しぼり菜種油かすを使用しています。菜種を圧搾絞りという薬剤を使用しない昔ながらの製法で絞ったもので、安心かなと思い使っています。
ちなみに10kgのを買ったらベランダ菜園には多すぎでした。まったくなくならない。
腐葉土&近所の土
腐葉土や近所の土というのは、発酵してくれる微生物を入れる目的で使用します。
できれば近所の山の、白かびが生えた分解されかけの落ち葉(=腐植)がおすすめです。その土地の菌を使用した方がいいと思うからです。
なければ腐葉土だけでも大丈夫です。
簡単!ぼかし肥料の作り方
それでは、ぼかし肥料を作ります!
①水以外の材料をまぜる

大きめのビニール袋(ゴミ袋でもOK)を用意し、水以外の材料を入れます。
※今回は、米ぬか1500g、油かす500g、腐葉土と腐植それぞれ一握りくらい使用しました。
ビニール袋の口を手で押さえるか結ぶかして、振ってよく混ぜます。(簡単に混ざります)
薄いビニール袋の場合は、2重にした方が破れにくいのでいいかも。
②水を少しずつ入れながらまぜる
水は入れすぎないように、少量ずつ入れて混ぜて確認しながら調整します!
水は、ギュッと握ると固まり、軽くつつくと固まりが崩れるくらいが適量です。(袋の上から握ると手も汚れません)

※参考までに、①の材料で水は約1㍑約2㍑使用しました。(2020.9.7訂正)
③空気をしっかり抜いて結ぶ

材料をひとかたまりにします。
嫌気発酵させるので、しっかりと空気を抜きます。
④日の当たらない場所で放置
約1カ月くらい放置します。真冬に作った場合は2~3カ月かかることもあります。
作り方は、以上です!手も汚れないし、後片付けも楽です♪
ぼかし肥料の完成の目安
約1カ月後、袋を開けてみて発酵した匂いがしたら完成です。
12月に作ると完成は2月か3月、2月下旬から3月に作ると1カ月くらいでできあがる感じかな。寒い地域はもっとかかると思います。
私が作る場合、最初はリンゴ酢のような香りがし、だんだん味噌ような香りがすることが多いです。ヨーグルトの香りという人もよく聞きます。
発酵が進むと白カビも生えてきますが、発酵している証拠でそのまま使用できます。
ぼかし肥料の保存

そのまま口を閉めて保存します。ジップロックなどに小分けにすると使い勝手がいいです。(その際も空気は抜く)
発酵が進むと肥料効果も弱まっていくので、数カ月など早めに使用したほうがいいです。
私は春に作り、秋野菜くらいまで使用しちゃっていますが。その場合、最初の頃は少量でもよく効きますが、発酵が進みすぎると肥料分が抜けていくようで量も多めに使用しなきゃいけなくなってきます。
発酵には湿度が必要なので、乾燥させることで発酵を抑えることもできます。
しかし、何度か空気にさらして乾燥させようとしたことがありますが、どうしてもアンモニア発酵に変わり臭いがしてしまうので、乾燥させるのは諦めました。
肥料の配合

肥料の配合について、補足しておきます。
米ぬかと油かす
チッソ・リン酸・カリウムは、肥料の三要素と言われています。
チッソは葉や茎の成長、リン酸は花や実、カリウムは根の成長に働きかけます。
米ぬかは、リン酸が豊富。チッソや少量のカリウムも含みます。
油かすは、チッソが豊富です。
この2つをブレンドすることで、葉ものにも実ものにも効果的なバランスのぼかし肥料を作ることができます。
米ぬか:油かす=3:1
この配合バランスが、花や実もの野菜にも葉も野菜にも使えて万能で使いやすく、最近はこの割合でいつも作っています。
この場合、チッソ・リン酸・カリウムの成分量は4:6:1くらいかなぁと思います。
米ぬか:油かす=2:1
葉物野菜に使用するなら油かすを増やして、この配合にしてもいいと思います。ただし、ミニトマトに使用したら、どうしてもチッソが多くてリン酸が少ないという症状が出てしまったので実もの野菜には向かなかったです。
使用する米ぬかと油かすの種類によっても、違いは出てきます。
土の肥料バランス、育てる植物によってなど、だんだん自分に適した配合を見つけていくといいと思います。
他に入れてもいい有機質肥料
米ぬかと油かすで作成するぼかし肥料は、カリウムの成分が少ないです。
植物の成長には、他にも微量要素・ミネラルも必要です。
以下の有機質肥料をぼかし肥料の材料に含めたり、元肥や追肥として与えることも可能です。
草木灰
草木灰は、カリウムを含みます。土壌の酸度をアルカリにする力もあります。
もみ殻くんたん
微量のカリウムとカルシウムを含み、土壌の酸度をアルカリに傾けます。通気性や排水性が良くなり微生物の住みやすい環境にします。
牡蠣殻石灰
カルシウムを含み、土壌の酸度をアルカリに傾けます。マンガン、ホウ素、亜鉛といったミネラルも含んでいます。
まとめ
以上、簡単なぼかし肥料の作り方、成分についてまとめてみました。
肥料は過剰に与えてしまうと、生育に障害が出たり虫を呼んだりしてしまいます。作成したぼかし肥料は、少量ずつ様子を見ながら与えるのがいいかと思います。
ぼかし肥料については、ひとまず完成形の記事になりますが、今後も得た情報があれば、追記していこうと思います。
ちなみに、プランター栽培で使用する場合のぼかし肥料の効果的な使い方については、別の記事にまとめています。ちょっと独特な内容となってはいますが…興味がありましたらご覧下さい↓